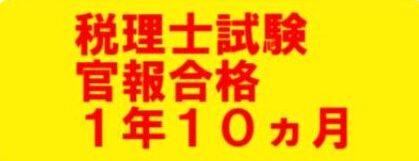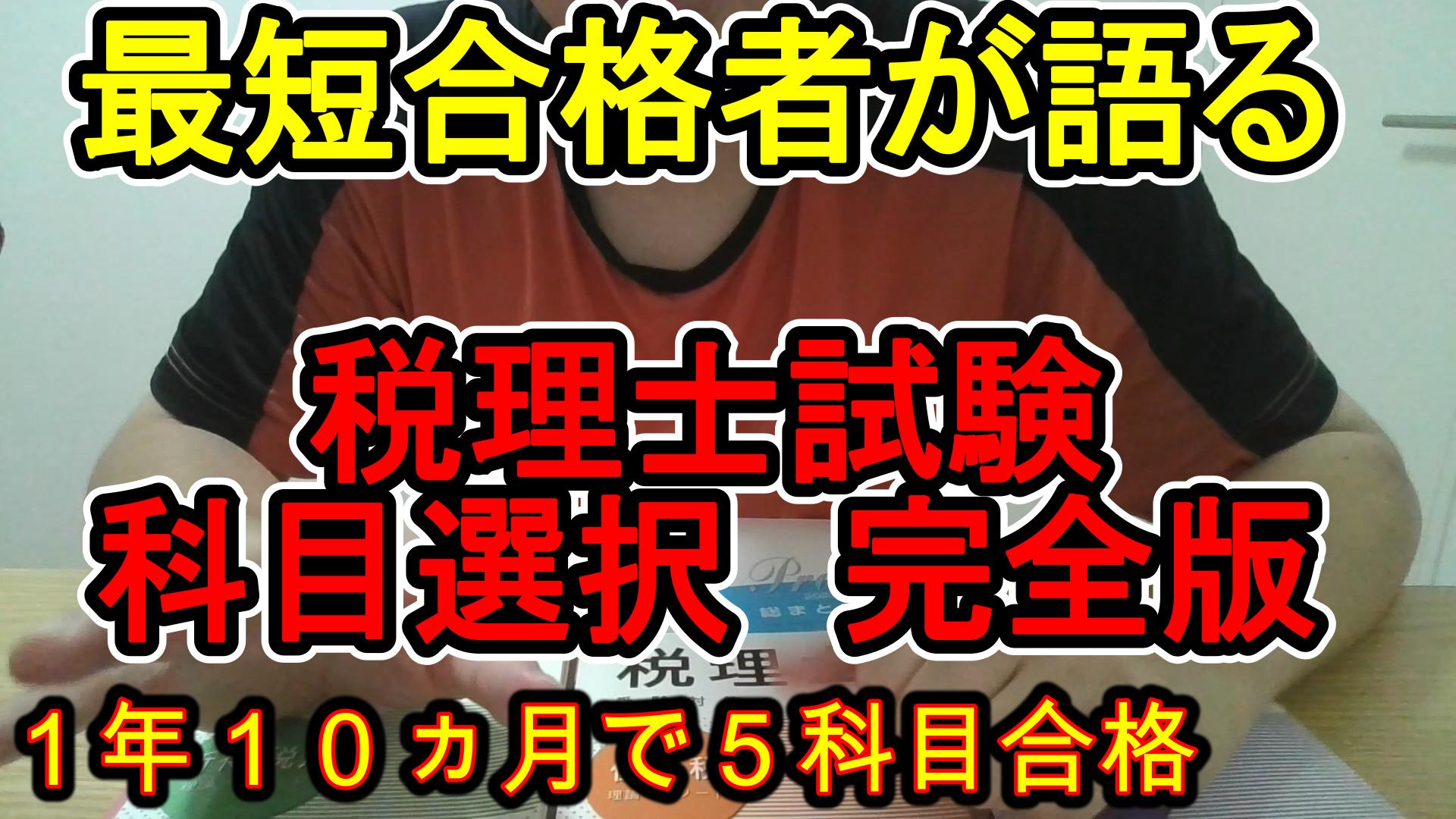税理士試験を1年10ヶ月で科目合格した経験をもとに、科目選択のポイントや勉強時間の目安、受験者層の情報まで徹底解説します!
目次
📌 必須科目と選択科目について
まず、税理士試験には必ず受けなければいけない科目があります。簿記論と財務諸論です。これ以外の科目は基本的に自由に選べますが、所得税法と法人税法のどちらかは必ず受験する必要があります。
残りの2科目は、自分の状況や得意分野に応じて自由に選択可能です。
🎯 科目選択の判断軸6つ
科目を選ぶ際の判断基準は大きく以下の6つです:
- 理論のボリューム
- 実務で使うかどうか/勉強スピード重視か
- 受験者層のレベル
- 受験者数の多さ
- 計算・理論の得意不得意
- 予備校の選択
📚 理論のボリュームの違い
科目によって覚える理論の量は大きく異なります。
- 所得税法:約188ページ(暗記量が多い)
- 法人税法:所得税に次いで多い
- 相続税・消費税:比較的ボリューム大
- 手税:約66ページ(少なめ)
ボリュームが多い科目は勉強時間も長くかかりますが、少ない科目は満点勝負になりやすいです。
⚖️ 実務重視かスピード重視か
法人税法・消費税法は実務でよく使う科目です。私は一般企業の経理経験がありますが、実務では法人税・消費税がメインで、所得税・住民税・酒税はあまり使う機会はありませんでした。
そのため、短期合格を目指すなら手税などのミニ科目がおすすめです。
👥 受験者層と人数の違い
科目によって受験者層や人数も大きく異なります:
- 消費税:約7000人(受験者多数)
- 法人税:約3500人
- 相続税:約2500人
- 所得税:約1000人
- 住民税:約460人
- 酒税:約500人
受験者が少ない科目は、勉強範囲を完璧に仕上げれば高確率で合格できます。
💡 科目の相性と得意分野
計算が得意なら手税や固定資産税、理論が得意なら国税長・相続税がおすすめです。また、所得税と住民税は範囲がほぼ同じなのでセットで受けると効率的です。
🏫 予備校選びも重要
主な予備校は以下の通り:
- 大原:合格者の半数が利用、全科目対応
- タック:大原に次ぐ、全科目対応
- LEC / ネットスクール:科目限定
- スタディング:簿記論・財務諸論に最適、Web完結で便利
科目や学習スタイルに合った予備校を選ぶことで効率的に学習可能です。
📝 まとめ
税理士試験の科目選択のポイントは以下の通りです:
- 理論のボリュームを確認する
- 実務重視か短期合格かで選択
- 受験者層・人数で難易度を把握
- 計算・理論の得意不得意を考慮
- 科目の相性やセット受験の効率を考える
- 予備校のカリキュラムを比較・選択
💡 私の経験から言うと、短期合格を狙うなら手税・住民税などのミニ科目がおすすめです。所得税は勉強時間も膨大で、短期合格は難しい傾向があります。
この情報をもとに、あなたに最適な科目選択を考えてみてくださいね!📘