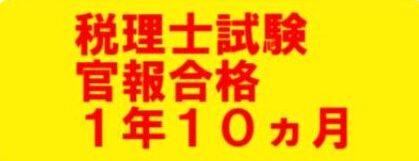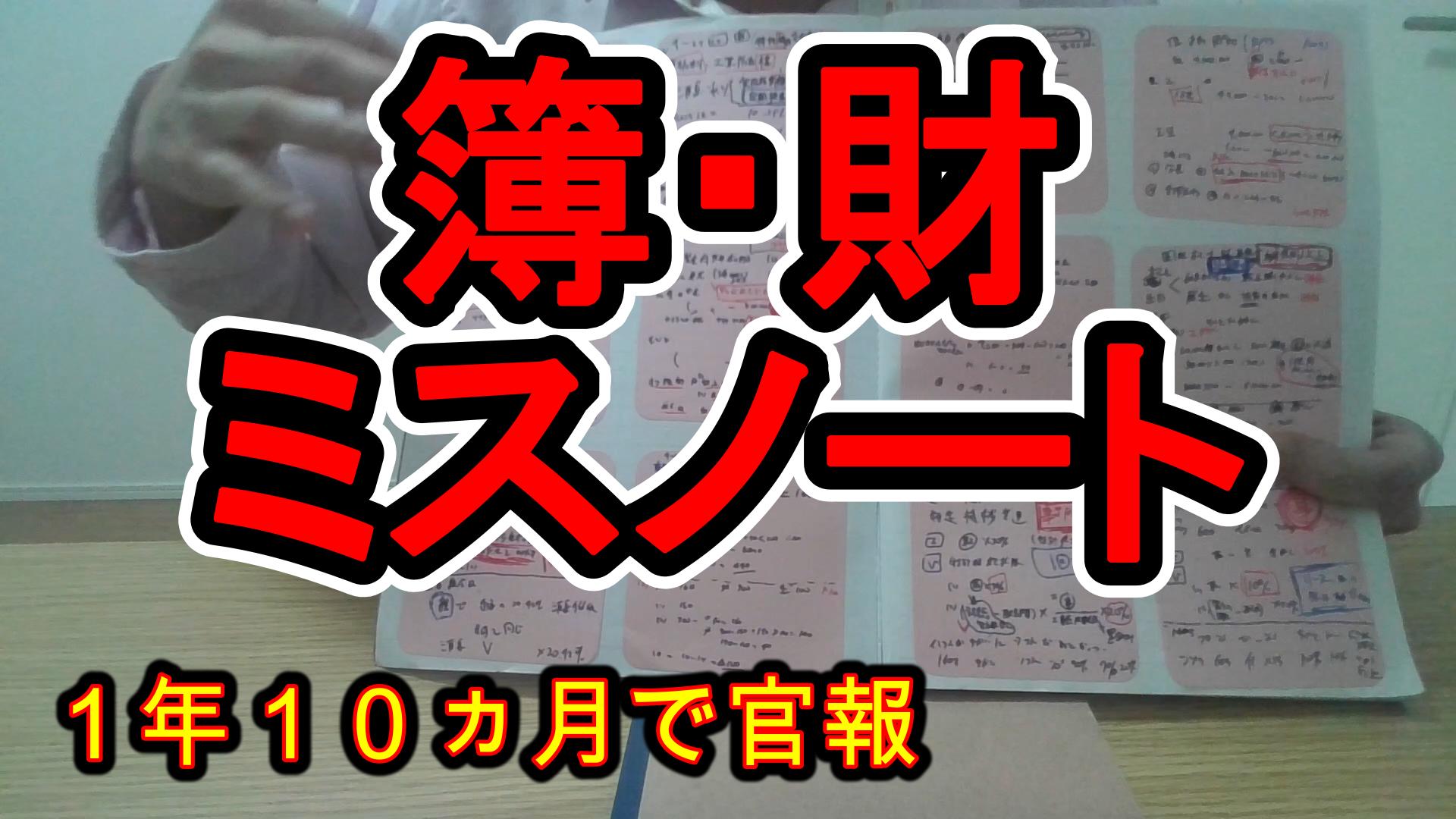皆さんこんにちは、ゆうりです。今回は「ミスノート」について、実際に自分が試験直前期に使っていたノートをベースに、どう作ってどう使えば効果的かを分かりやすくまとめます。僕は直前(5月頃)からミスノートを本格的に使い始めました。完璧な教科書的ノートではないですが、直前の“点検ツール”としては十分機能しました。
目次
ミスノートって何を書けばいい?
僕の基本ルールはシンプル:
- 模試や過去問で「間違えた箇所」を記録する
- 「何回間違えたか」を分かるようにする(頻度管理)
- 部分点・暗算ミス・電卓ミスなど原因を書き分ける
書く内容の具体例
- 科目:簿記論/問題番号:第3問(個別)
- 間違いの種類:仕訳の勘定科目の入れ替え(例:見払金 ↔ 見払利息)
- 原因:理論の誤認/注意不足(電卓入力ミス)
- 頻度:①(1回目)、②(2回目)→ 間違えた回数を右側に追記
- 対策メモ:次は●●のチェックリストを作る/仕訳ルールを一行で復習
僕がやっていた“頻度マーク”の付け方
間違えた回数を左端に「1」「2」「3」と記入していく方法です。これにより、模試を重ねるごとに「本当に直さないといけないミス」が可視化できます。
- 1回目:小さなチェック → 備考にメモ
- 2回目:要注意 → 再発防止フラグを立てる
- 3回目以降:致命的 → 優先的に復習(本試験1時間前に必ず目を通す)
よく書いていた“代表的なミス”
僕が頻繁にやっていたミスは以下の通りです(簿記/財表/税法で共通):
- 勘定科目の入れ替え(雑収入 ↔ 雑損失、見払金 ↔ 見払利息など)
- 桁や1円の入れ間違い(端数処理ミス)
- 電卓の入力ミス(例:810を510で打つ等)
- 集計は合っているが足し算ミス(電卓ミス)
- 前受金・前受収益の月数ミス(期間配分ミス)
- 税額計算の効果忘れ(税効果等)
- マイナスや配当の扱い忘れ(マイTVの加算忘れ)
- 連結の内部利益や引当金の処理ミス(連結が苦手な自分は仕訳だけ覚える作戦)
ミスノートのフォーマット(おすすめ)
手書き派の方向けに、僕が実際に近い形で使っていたテンプレを提示します。A4ノートの片面を使って一問一ミスを短くまとめるイメージです。 【日付】 202X/5/12 【科目】 簿記論(模試) 【問題】 第3問(個別) 【ミス内容】 見払金と見払利息を入れ替え 【回数】 ① 【原因】 勘定科目の意味の理解不足/確認不足 【対策】 仕訳ルールを1行でまとめる(試験1時間前に読む)
試験直前(1時間前)の使い方
- 「回数が3以上」「合格に直結するミス」だけをピックアップして見る
- 長文の解説は避け、仕訳・チェックリスト・再発防止ポイントだけ目で追う
- 声に出して読むと緊張時でも記憶に残りやすい(短いフレーズで)
ワンポイント:僕は連結が苦手だったので、連結だけは「仕訳一覧」を作って本試験の1時間前に流し読みしていました。意味まで理解しきれない分野は、まず「仕訳だけ切れる」状態にすると安定します。
税法(所得税など)のミスノート運用
税法系は紙面に付箋を貼る方式で運用していました。ダイソーの四角い付箋(大きめ)が使いやすいです。
やり方:科目ごとにノートを分け、付箋に「間違った論点+要復習ポイント」を書いて貼る → 定期的に付箋を見直す → 見なくなったら剥がす(=克服済み)
具体的な“修正アクション”例
| ミス | 原因 | 対策(次回までにやること) |
|---|---|---|
| 見払金と見払利息を入れ替え | 語感で判断している | それぞれの勘定の意味を一文で書く・仕訳ルールを暗唱 |
| 電卓で桁落ち(810→510) | 押し間違い/位置の癖 | 電卓配置を統一/必ず小数点を意識する→模試でのみ意識的にチェック |
| 前受収益の月数ミス | 期間按分を忘れる | 「期間按分テンプレ」を作って見る(例:受取日→期限→按分式) |
おすすめの道具(コスパ良し)
- A4ノート or 無地のルーズリーフ(書きやすさ重視)
- ダイソーの大きめ付箋(税法用)
- 色付きペン(頻度マークや重要度を色で分ける)
- 電卓は自分専用の配置に慣れておく
よくある迷いと僕の答え
Q:ミスノートはいつから付ければいい?
A:理想は早め。ただし僕は直前(5月)から本格運用で合格しました。大事なのは「見直す頻度」と「直すための行動」を確保すること。
Q:細かく書きすぎて続かない…
A:むしろ「短く・シンプル」に。原因と対策(短文1行)だけを書けば続けやすいです。
まとめ:ミスノートでやるべきこと(3ステップ)
- 模試で間違えたらすぐ書く(原因と短い対策)
- 回数で優先順位をつける(1→2→3)
- 本試験1時間前は「3回以上」or「合否に直結するミス」だけ見る
短いチェックリスト(印刷して使える)